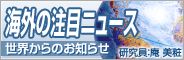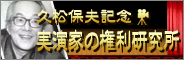2009年の深い悲しみ 歌人にして元最高裁判事・弁護士 橋元四郎平(はしもと しろうへい)先生のこと
棚野正士備忘録
2009.12.8 IT企業法務研究所代表研究員 棚野正士
1.橋元先生の急逝
今年2009年8月1日、橋元四郎平弁護士が急逝された。86歳であった。 橋元先生は元日本弁護士連合会事務総長、最高裁判所判事で勲一等瑞宝章受章者でもあり、日本の法曹界の最高峰に立たれた法律家であるが、一方、1998年(平成10年)宮中歌会始の召人を務められた著名な歌人であった。 雑誌「企業と知的財産438号」(日本科学振興財団発行。本号の表紙は橋元先生)の対談「法律家と歌人の人生」の中で、“ぼくは法律家ですけど、法律より文学や芸術、いわば法律以外の文化に対する関心の方が強いですから・・・”と話しているが、橋元先生は法律家であるだけでなく、歌人であり、こけしや三春人形の収集家で著名な研究家でもあった。又、オペラ、バレエなど舞台芸術への造詣が深く、日本だけでなくヨーロッパにおける公演もよく現地で楽しんでおられた。以前、ザルツブルグのオペラを紋付袴に正装して、着物姿の奥様とお二人で観に行った事を楽しそうに話しておられた。

法律専門書以外に、橋元先生は歌人として、「歌集 三春」(小沢書店)、「歌集 辛夷ひらく」(短歌新聞社)を出版されているが(写真)、こけしや三春人形でも「らっこコレクション図鑑」(グラフィック社)、「三春人形」(東峰出版)、「こけしの旅」(平凡社)、「ふくしまのこけし」(福島中央テレビ)など多くの名著を残されている。
2.橋元先生と久松保夫
橋元四郎平弁護士は、1972年6月社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)の法律顧問に就任された。芸団協との縁は久松保夫専務理事(故人)とのこけしが取り持つ縁であった。 その年、わたくしは芸団協職員として先生にお目にかかり、以後38年に亘り指導を得た。橋元先生は、法曹界の頂点に立つ法律家で同時に著名な歌人であり、又、こけしや三春人形の研究家であり、現代有数の文化人であり、一職員からは聳え立つ気高い山脈のような存在である。山脈に分け入って橋元先生を語る資格はわたくしにはないが、一団体の一職員から見た大山脈の一端に触れてみたい。言葉を替えれば、本稿はむかしの職員のあたまに浮かんだ「橋元四郎平先生の主題による芸団協変奏曲」であると言ったほうがよいかも知れない。橋元先生をテーマに実演家の組織という曲をどう奏でるかという想いで書いたわたくしなりの追悼文である。 久松専務理事は芸団協の創立者で、著作権法上の実演家の権利を確立した組織人であった。又、売れっ子のスター俳優であったが、同時に日本有数のこけしの収集家であり、人形の研究家であった。日本の実演家の権利と組織は久松専務理事の理念、思想により形成されてきたが、久松専務理事は俳優であるだけでなく、芸能の研究家、民俗文化の研究家、人形の研究家であった。 芸団協法律顧問である橋元四郎平弁護士は「久松保夫著作集 役者人生奮戦記」(芸団協発行)の「追想」欄で、「心のなかの久松さん」と題してこう語っている。 「久松さんとの出会いは、こけしによってである。・・・古品こけしの入札で、いつも最高価格で多くのこけしを落札するのが、私より前に入会していた久松さんであった。」 「私が久松さんの終生の事業である芸能人の組織づくりに、弁護士として関わるようになったのは、昭和38年9月、「日本放送芸能家協会(略称「放芸協」) (筆者注:放芸協は芸団協の会員団体で、現在は「日本俳優連合」)」の設立がきっかけである。このとき、私は、協会の定款、規約の作成を依頼され、設立総会にも出席し、法律顧問となった。」 「この頃から、久松さんは、著作権法の勉強を開始し、私がお貸しした著作権法の文献全部を、大学ノート数冊ノートしながら読破するという猛勉強をした。その成果が、昭和46年6月発行の『忘れられている著作権―芸能人は法律でどのように護られているかー』(筆者注:「久松保夫著作集 役者人生奮戦記」(芸団協発行)所収)である。この書は、著作権法(旧法)のもとでの芸能人の法的権利について、全面的に論じ、問題を提起したわが国始めての著作として、注目された。」 「この書の執筆中から、文化庁において、著作権法の全面改正の作業が進行、久松さんは、新著作権法に、芸能人の権利を十分に盛り込もうとして、全力を傾注した。その運動を推進しながら、久松さんは、専門芸能家の団体すべてを結集する全国統一組織を作ることに努力し、遂に昭和40年12月に「日本芸能実演家団体協議会」(略称「芸団協」)を設立するに至った。会長は徳川夢声、久松さんは専務理事として、組織の運営の中心を担った。私が「芸団協」の法律顧問に就任したのは、数年後であるが、その前から、事実上、芸団協関係の法律問題の相談を受けており、久松専務理事とは、芸能実演家の諸権利の確立と強化、芸団協の組織拡充等全般にわたり、終始意見を交換した。芸団協の業務全般にわたり、労苦を共にしたといって過言ではない。」
3.橋元先生と芸団協
こけしが取り持つ縁で、日本有数の法律家を顧問に迎えたことは、芸団協の歴史にとって何より幸せであった。 「久松保夫著作集 役者人生奮戦記」のあとがきに、わたくしはこう書いた。 「久松保夫という人は俳優であり、組織人であり、芸能や民俗学の研究家であり、こけしの収集家であり、人形の研究家であり、また、近世古文書の学徒でもあった。多くの山々が連なる山脈を思わせるような人であった。しかも、連なる山々の一つ一つが高く大きかった。そして、その山々はお互いに関連しあい、山脈全体として調和をとり、あたかもひとつの交響詩を形成する感があった。」 わたくしは、橋元四郎平先生を思うとき、先生もやはり大きな山々が連なる山脈であり、大きく響く交響詩であるような気がする。 その二つの山脈が共鳴し合い、二つの交響詩が響き合って芸団協を支え、芸能人の組織、権利を創り上げてきたのだろうか。 芸団協は1965年12月7日設立されたが(会長徳川夢声、正会員団体21)、その設立趣意書でこう述べている。 「わが国の芸能界は、古い歴史的伝統に支えられ、それぞれの時代に於てすぐれた代表的芸能家を生み出しながら、世界に誇りうる数々の民族文化的遺産を継承発展させつつ今日にいたっております。然しながら、実際にその創造にたずさわって来た芸能家は、旧来必ずしもそれにふさわしい所遇を受けて来なかったのが実情でありました。殊に昨今は、映画放送など視聴覚文化を中心とするマスコミ産業の驚異的発展に伴い、国民文化の中に占める『芸能』の位置も相対的に高められ、その直接の担い手である芸能実演家の社会的責務も又一段と重大になって来て居ります。 このような役割りの重大さにもかかわらず、一般にまだまだ芸能実演家の社会的地位は低く、他の諸分野に比して権利よう護、社会保障その他福祉制度確立の面でも著しい立おくれを示しているのが現実であります。 今日芸能界は、『著作権法の全面的改正』という、全芸能実演家にとってまさに人格権と生活権の根底を左右する大問題をかかえ、かつてないさしせまった状況を迎えているのでありますが、遺憾ながら芸能界は全体としてこれに対する有効な方策を講じ得るような態勢にあるとは言い難いのであります。 私共芸能実演家はこの際はっきりと、将来に向かって眼を開き、この法改正の帰趨を重大なる関心を持って見守ると共に、正に悔いを百年の後に残さないために今後共強力に働きかけて行かねばなりません。」(以下、省略) 芸能実演家が始めて大同団結するという喜びに満ちたこの設立趣意書は、久松保夫が中心になって橋元先生の指導を得て執筆されたと推察されるが、ここには、「技術の向上、社会的地位の向上、福利厚生の三本の柱を中心に、自己の属する諸組織を挙げて総結集を図り、公益法人としての『日本芸能実演家団体協議会』を設立する。」という強い決意が盛り込まれ、以後、「技術の向上」「社会的地位の向上」「福利厚生」の三本は芸団協の中心柱となった。 芸団協は1972年6月1日付けで、橋元先生に法律顧問を委嘱し、以後、芸団協の法律問題、特に著作隣接権に関わる諸課題、芸団協の組織、運営に関わる課題等すべてにわたって指導を得た。 1975年、坂東三津五郎前会長の跡を継いで芸団協会長に就任した中村歌右衛門、専務理事久松保夫の思想で芸団協はその姿を形成してきたが、組織は思想、理念だけでは姿を形づくることは出来ない。橋元先生という芸術家の魂を理解する大法律家がその組織を支えたからこそ40数年にわたって成長し変化してきたと考えられる。 例えば、1993年、芸団協がその組織の中に実演家著作隣接権センター(CPRA)を設立したことは、芸団協の歴史的変革であったが、その難しい課題を指導、応援し、整備したのも橋元先生であった。1993年のCPRA創立時、又、1998年のCPRA見直し時など要の時々に橋元先生の指導と支持を得た。2001年、定款変更によりCPRAの位置づけを明確にし、会員資格を拡充したが、それに伴う改正条文の草稿は橋元先生自らが筆をとった。橋元先生の指導がなければ今日の実演家の統括的組織は出来ていないと考えられる。
4.橋元先生と中村歌右衛門
1975年から21年間に亘って会長を務めた不世出の大芸術家中村歌右衛門は、俳優、音楽家、舞踊家、演芸家等々すべての分野にわたる実演家75,000人をその芸術家としての思想で見事に統括した。 橋元先生は会長中村歌右衛門に深い敬愛の念を抱き続けていた。 中村歌右衛門会長は1996年、勲一等瑞宝章を受章しているが、そのお祝いを、橋元先生は機関紙「芸団協」(1996年12月10日付け)で次のように述べている。 「芸団協20周年記念の主催公演が昭和60年2月19日に開催され、歌右衛門会長は、番組の一つである歌舞伎「隅田川」で狂女「斑女の前」を演じた。亡きわが子の姿を幻視し幻覚する果てに残る孤独な母親の絶望を、会長は、完璧に表現して、満員の観客に深い感動を与えた。」「その「墨田川」を会長は、昭和60年8月に佐渡島で開かれた「第1回全日本子どものための舞台芸術大祭典」の記念公演でも演じた。」 「公演の前に会長は大祭典の名誉会長として挨拶したが、「隅田川」について、「子ども衆に負けないように勤めたい」と語った。その言葉のとおり、会長の演ずる「墨田川」は絶大な感動を人々に与えた(芸団協春秋20年)。」 「会長は、昭和39年に、47歳という最年少記録で日本芸術院会員に選ばれ、同43年には重要無形文化財(人間国宝)に認定され、54年11月には文化勲章の栄誉に輝いた。このような天下の名優が、外国人をも感動させるような至高の芸を「子ども衆」のために、「子ども衆に負けないように」と、遠路わざわざ佐渡に赴いて演じたのである。この誠実で謙虚な人柄と並々ならぬ使命感に、私は深い感銘を覚えざるを得ない。」 中村歌右衛門会長は「芸術家であること」を至上命題にし、芸団協は「芸術家の団体」であることを指導原理にしてきた。 「芸団協春秋20年」(1987年発行)の中で、中村歌右衛門は芸団協の方針、基本理念についてこう語っている。(同書4ページ) 「やはりね、権利だとか法律だとかいうのも結構だけれどね、芸術家の団体だということを忘れてはいけないと思いますよ。」 歌右衛門会長にとって、「芸術家の団体」であることがすべての基本であり、基本思想であるという強い想いがあった。そして、中村歌右衛門は事あるごとに、「芸術家の地位の向上」を唱え主張した。 大芸術家中村歌右衛門会長を畏敬し会長の理念を支えた橋元先生を、歌右衛門会長も又尊敬し精神的支えにした。 中村歌右衛門、久松保夫、橋元四郎平というたぐい稀な人達を核にして、あこや貝が真珠を育てるように芸術家の統一的組織が形成されていった。上質の核がなければ上質の真珠は生まれない。日本の実演家は歴史の節目節目に核になる優れた人材を得たと思われる。
5.身分から契約へ(橋元先生著作権人語)
「コピライト」(1996年5月号。著作権情報センター発行)に橋元先生は、“著作権人語 当世風「身分から契約へ」”を書いている。 映画の著作物において録音・録画された実演には、実演家の録音・録画権が働かないという問題で実演家の契約問題を取り上げており、次のような趣旨である。 「現実は、実演家が自由な契約によって権利を確保することがきわめて困難な状況にあるといってよい。」と述べ、「ここで想起されるのは、「身分から契約へ」という有名な言葉である。これはイギリスの法制史家メインの「古代法」(1861年)第5章の終りにある「進歩的な社会の推移は、今までのところ、身分より契約への推移であった」に由来する(我妻栄・民主主義の私法原理より再引用)。この場合の身分とは、自由人・奴隷・家長・家族などのような人的な地位であって、古代・中世では、個人の社会生活関係はこのような身分によって定まり、本人の意思に基づいて自由に定められる範囲が極めて少なかったが、文化の発達に伴い、自由な契約によって定められる範囲がしだいに増してきており、そこに社会の進歩をみることができる、というのである(有斐閣・新法律学辞典による)。 今日の資本主義社会では、上記のような人的な地位によって法律関係が定まるという現象は、ほとんど姿を消した。そして、人的な地位としての「身分」のかわりに、使用者や労働者としての地位のような「社会的身分」が現れるようになった。また、資本主義の発達によって、契約条件を一方的に提示し締結をする、いわゆる「付合契約」が多く見られるようになった。しかし、実演家と映画会社の契約では付合契約とまではいえないであろう。あえていえば、実演家という「社会的身分」によって、権利ないし法律関係が定まることであろうか。」 「「映画」の世界では、かつての「身分から契約へ」が、新たな形で、未だ「身分」の段階にとどまっているとの感をいだかざるを得ない。そうであれば、早く「契約」の段階に進んでほしいものである。」 橋元先生の「身分から契約へ」という指摘はまことに卓見であり、先生の御遺言であるように思われる。先生が亡くなってから、「コピライト」(1996.5)の「著作権人語:当世風「身分から契約へ」」を読み返し、改めてそう思う。日常の猥雑さに捕われていると、この基本理念を置き忘れてしまう。 芸団協の50年は本来まさに、“身分から契約へ”の時代の変化を見据えた実演家達の闘いではなかっただろうか。 芸団協の設立趣意書も、久松専務理事の組織づくりの原点も、又、中村歌右衛門会長の基本姿勢もすべて“身分から契約へ”の流れに内在する課題ではないか。今、日本の実演家、いや芸術家全体がこの問題を自ら問わなければならないように思う。
6.橋元先生と三春
橋元四郎平先生の「歌集 三春」の序文で、詩人飯島耕一氏は、「三春、福島県の中通り地方のほぼ中央、阿武隈高地西麓にある町。陸奥国の城下町。古く御春といわれ、春に梅と桜と桃が一度に咲くというので三春となった。」と述べている。その三春は橋元先生のふるさとである。 「コピライト」(1997.6)に橋元先生は、「歌集「三春」をめぐって」を書いているが、その中で、「三春(福島県三春町)は、私の生まれ育った故郷であり、私は、旧制中学を卒業するまで三春に暮らした。20数年前、町の郊外の父祖伝来の地に山荘を建て、年に数回滞在して自然の風光を楽しんでいる。」「その「三春山荘」は、静かな丘陵の中にあり、まわりは雑木林で、松と風が風情を添えている。夏はとくに茅蜩(ひぐらし)の声が涼やかに全山にひびく。」と述べている。 1998年(平成10年)1月14日の歌会始の儀で、橋元先生は、召人として陛下に應制歌を詠進されている。
芽ふきゆく木末の 空はしつかなりはや しに入りて道つつ 久加母 (芽ぶきゆく木末(こぬれ)の空はしづかなり林に入りて道つづくかも)
召人橋元先生は覚え書「召人のこと」の中に、「召人は、真っ先に拝謁し、お言葉を賜る。私は郷里三春の早春の情景を思い浮かべて作歌した旨を言上した。」と書かれている。又、その文書の中に、「歌はもともと歌われるものであり、万葉以来なされてきたように、歌うものとして詠まれ、歌うように音読されるべきものであろう。そう考えると、歌会始における披講は、注目すべき行事であり、もっと国民が関心を抱いて然るべきであると思う。このことを、召人に定められて痛感すると同時に、歌会始に参列し、古式ゆかしい「披講」をまのあたり体験できたのは得がたい経験であり、生涯忘れえないこととして心から光栄に思うものである。」と述べられている。 橋元四郎平先生は貴人の心を持ち続けた法律家で文人であった。
(結び)
歌会始で陛下に詠進された應制歌「芽ふきゆく木末の空はしつかなりはやしに入りて道つつ久加母」は、何度繰り返し読んでも不思議な感動がある。自然を詠んだ自然な歌であるが、何回口にしても、そのたびにわたくしはこみ上げてくるなみだを抑えきれない。歌は不思議な力をもっているのだろうか。 橋元先生は、2009年9月12日、納骨のため故郷・三春に奥様に伴われて帰られた。その二日前に、わたくしは東京杉並区のお宅に伺いお別れの挨拶をした。 先生にお別れをしながら、“兎追いし かの山 小鮒釣りし かの川”で始まる高野辰之作詞「故郷」を口ずさんでいた。 “志(こころざし)を はたして いつの日にか 帰らん 山は青き 故郷 水は清き 故郷“ いつか、先生の三春山荘の近くにあるという天然記念物の「滝桜」が満開の時に、橋元四郎平先生を訪ねてみたい。
コメントを投稿する
※コメントは管理者による承認後に掲載されます。