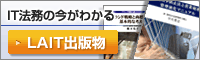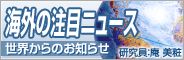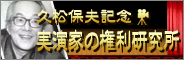【特別レポート】芸術文化史上画期的な運動“Culture First はじめに文化ありき”
(記:代表主任研究員 棚野正士)
「Culture First はじめに文化ありき」の発表イベントが、2008年1月15日、東京の“丸ビルホール”で開かれた。主催はデジタル私的録画問題に関する権利者会議28団体(賛同団体を含め87の芸術文化団体が関与)。
この運動はヨーロッパで発足した「Culture First!連合」を受けたものである。当日の資料によると、「ヨーロッパでは情報通信技術・電子機器業界からの強い圧力で、欧州委員会が、2005年末、DRM(著作権保護技術)などの新しい技術、機器を考慮し、補償金制度は段階的な廃止へ向けて検討する意向を表明したことに対して、CISAC/BIEM(著作権協会国際連合/録音権協会国際事務局)による2006年1月の意見表明をきっかけに、2006年9月、Culture連合が結成された。その結果、Culture First!連合は、2006年12月、欧州委員会委員長にそうした見直し計画を放棄させることに成功した。」という背景がある。
日本における運動は、私的録音録画補償金制度の適正な見直しを実現するために、ヨーロッパで成果を上げたCulture First!連合を参考に始められた動きである。
“私的録音録画問題は足掛け4年文化庁私的録音録画小委員会で議論”(椎名和夫CPRA運営委員・同小委員会委員)されているが、この4年という時間が“Culture First”というエポック・メーキングな運動を生み出したと言える。迅速に現実的対応をすべき私的録音録画問題に4年という時間は長いが、しかし、それによって“Culture First”という芸術文化運動の“真珠”が生み出されたとすれば、無駄な時間ではなかったかも知れない。その真珠が輝きを増すかどうかは、権利者団体のハートと頭脳にある。
1月15日、発表イベントのセッションの中で、作曲家すぎやまこういち氏は“コンピューター、ソフトがなければただの箱”という言葉を織り込んで、ソフトウェアの大切さを訴えていたし(ビデオメッセージ)、慶應義塾大学教授岸博幸氏は“今、ソフトパワーが重要で、ソフトパワーを構成するのは文化である。Culture Firstの役割は、圧力組織としてロビーストの役割を果たすと共に啓蒙組織になれ”と運動への期待を語っていた。
なお、この日、椎名和夫氏から「Culture First」のシンボルマークと行動理念が紹介されて承認された。行動理念は次の通りである(当日配布資料から)。
- 文化の振興こそが、真の知財立国の実現につながることについて、国民の理解を求めるとともに、その役割を担っていくことを表明します。
- 経済の発展や情報社会の拡大を目的としたどんな提案や計画も、文化の担い手を犠牲にして進められることのないよう、関係者並びに政府の理解を求めます。
- 3. 知財先進国の経済発展を支えるのは、市場を賑わす種々の製品だけでなく、文化の担い手によって生み出される作品やコンテンツの豊かさと多様性でもあることを強調します。
以上
棚野正士 著